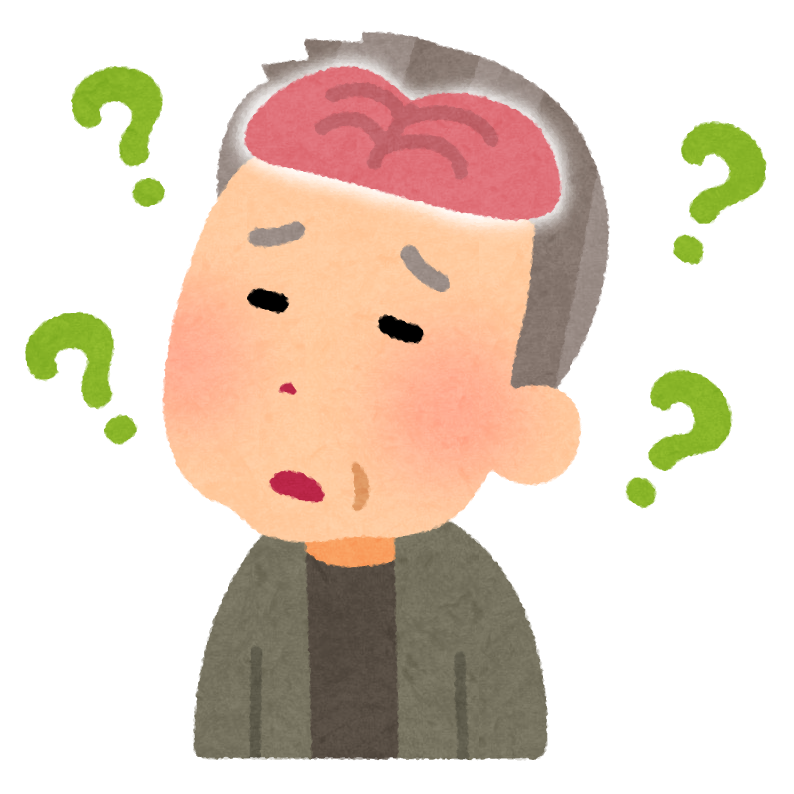身内の方の認知症対策はできていますか?
身内に高齢者がいらっしゃる方がまっさきに検討していただきたいことは「認知症対策」です。
特に財産や金銭トラブルが多い為、事前に対策を取る必要があります。
1. 親が認知症になったときに起きる財産管理トラブル
【認知症になってしまった時の問題点】
- 遺言などによる相続対策が難しくなる
重度の認知症と診断されると、法律上の「意思能力がない人」と判断されます。
「意思能力のない」状態で行われた相続対策(例えば遺言書作成や生前贈与)は無効になってしまいます。そのため認知症を発症する前に、もしくは症状が軽度のうちに遺言書を作成し、生前贈与をしておくことが大切です。 - 自宅の売却や不動産の活用ができない
認知症の程度が進行すると、「何かを買う・売る」などの意思表示を行うことが、能力的にも法律上もできなくなります。例えば、認知症の親が介護施設に入居した後、親の自宅を売却したくてもできなくなります。 - 預貯金を引き出すことができず、親族などが費用を立て替えざるを得ない
親が認知症になると、銀行の預金を一人で引き出すことができなくなる可能性があります。家族が代理で引き出そうとしても、本人が認知症により意思能力を失っていれば、代理権の授与は無効となります。結果的に介護や医療にかかる費用、さらには生活費さえ引き落とすことができなくなり、親族がその費用を負担することになります。こうした事態は、認知症の方に不利益を及ぼすばかりでなく、周囲の親族などにも大きな負担になり得るので、あらかじめ認知症対策を行っておくことが望ましいでしょう。
他にもこのようなトラブルが多いです
- どのような財産を所有しているのか忘れてしまう
- 悪徳商法や詐欺に引っかかりやすくなる
- 不必要な物を無駄に購入してしまう
2. 認知症対策に有効な3つの財産管理手法とは?
認知症になった場合、財産管理に支障を来すケースが多い為、信頼できる人にあらかじめ財産管理を託しておくことが有効です。
なお、任意後見と法定後見は成年後見制度の種類です。
<認知症対策に有効な財産管理手法のメリットとデメリットの一覧>
| 財産管理手法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 1.任意後見 | 信頼する人が本人に代わり契約締結などの法律行為をできる | 取消権がないため詐欺被害にあったときに守れない |
| 2.法定後見 | 本人の行為について取消権があるので詐欺などの被害に対し有効 | 本人の意思が確認できないため事前の認知症対策としては有効でない |
| 3.家族信託 | 信託の内容を自由に設計できるため本人の希望がかなう | 本人に代わって入院などの契約はできない |
※任意後見や法定後見は、家族信託との併用も可能